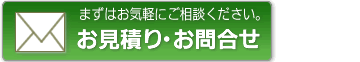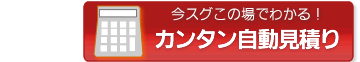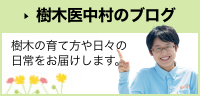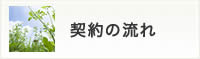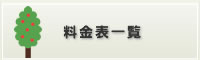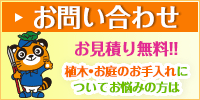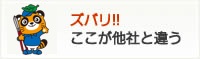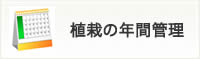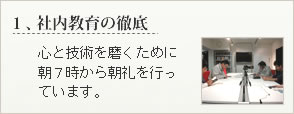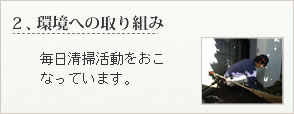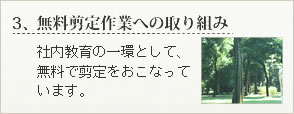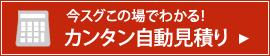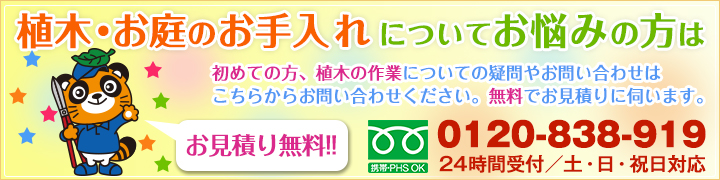お盆と「庭」の語源 ── ご先祖さまを迎える清めの場
お盆は、ご先祖さまの霊をお迎えし、感謝を伝える大切な時期です。
家の玄関や仏壇を整えるのはもちろん、庭先をきれいにするのもこの時期の習わしのひとつ。
実は「庭」という言葉そのものが、もともと 神さまやご先祖さまをお迎えする清められた場所 を意味していたことをご存じでしょうか。
「庭」のはじまりは「斎庭(ゆにわ)」
古代の日本では、神事や祭りを行うために特別に清められた場所を 「斎庭(ゆにわ)」 と呼びました。
「斎(いむ)」は、穢れを避けて心身を清めること。
「庭(にわ)」は、その祈りのために整えられた空間を指します。
神さまをお迎えする「ゆにわ」は、土を均し、草を刈り、道具を整えた神聖な場。
やがてその言葉が日常に広まり、家の外にある空き地や庭園も「にわ」と呼ばれるようになりました。
庭を整えることは、心を整えること
お盆前に庭を掃除する習慣は、ただ見た目を美しくするためだけではありません。
昔の人にとって庭は、ご先祖さまや神さまとの境界であり、祈りの舞台でした。
草木を整え、掃き清めることは、心の中のざわつきを鎮め、清らかな空気を呼び込む行いだったのです。
現代の「ゆにわ」を生きる
今の暮らしでは、昔のように大掛かりな祭場を作ることは少なくなりました。
けれど、鉢植えの草花を整えることも、玄関先を掃き清めることも、小さな「ゆにわ」を作る行いです。
そんな神聖な場所だと理解をし、私たちは日々の仕事を行っています。
お盆の時期こそ、庭やベランダを整え、迎え火のようにあたたかな空気でご先祖さまをお迎えしてみませんか。